令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
1.相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2.遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
※令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが義務化の対象です。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
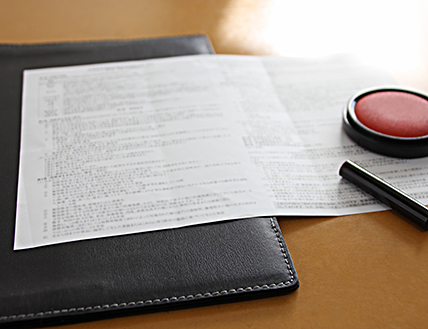
土地・不動産の名義変更
相続時の資産の約6割程度は不動産が占めると言われております。相続の手続きの中でもこの不動産登記は重要なポイントとなってきます。
不動産は容易に分割できず、高額な上、名義変更の手続き時は、戸籍謄本など書類取得以外にも、評価額の算定など、知識・時間・労力が必要で難しい手続きといえます。

相続手続・名義変更をしなかった場合
相続登記は「いつ頃までに手続きをする」という期限はありませんが、
相続手続(登記)をしておかないと、デメリットしかありません!
専門家へお早めにご相談下さい!
- 相続した不動産を売ることができない。(ただし、相続登記を前提としていれば可能なことがある)
- 不動産を担保に銀行からお金を借りるために必要な抵当権設定登記ができない
など、様々な弊害が生まれてしまいます。
相続手続の流れ
- 1被相続人の死亡(相続開始)
-
- 死亡届の提出(死亡届は、相続後7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します)
- 火葬許可申請書の提出
- 葬儀の準備
- 2葬儀
-
- 葬式費用の領収証など整理(相続財産から控除することができます。)
- 3相続財産の整理
-
- 遺言書の有無の確認(自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所での検認が必要になることがございます。)
- 相続人の確認
- 相続財産、債務の調査(相続放棄や限定承認をするか検討します。)
- 4相続放棄・限定承認 (必要に応じて)
- 必要に応じ、家庭裁判所で、相続放棄や限定承認の手続きを取ります。
相続放棄・限定承認は相続開始を知った日から3か月以内にする必要があります。
- 5遺産分割協議
-
- 遺産分割協議書の作成
- 6相続財産の名義変更や解約手続
-
- 預貯金の解約や名義変更
- 株式、有価証券の解約や名義変更
- 不動産(土地・建物)の相続登記
- 7被相続人の所得税申告と納税
※全ての方に必要な事ではございません。
- 8相続税の申告と納付
- 相続税の申告と納付は原則として相続開始後10か月以内にする必要があります。
※相続税に関するご相談は税理士もしくは税務署にお問合せください。


